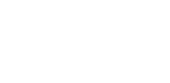恋が溢れて止まらない - 사랑이 넘쳐 멈추지 않아
愛子は周りを気にせずに、何かといえばキスをせがんだ。
아이는 주변을 신경쓰지 않고, 뭔가를 말하자면 키스를 졸랐다.
「あかん」
안돼(방언임...)
「なんで?」
왜?
「電車の中や」
전차 안이야
「かまへんやん」
상관없어 (방언)
混み合った車内で向き合うように立ち揺れていた俺たちは、ささやかに、さっとキスした。まるで銀行強盗を成し遂げた直後のような、緊張と解放が折り重なって頭がおかしくなりそうだった。
혼잡해진 차내에서 마주보듯이
「ククク」
「なにわろてんや」俺は小さい声で言った。
「あんた、耳赤くなってるで」
「ヤな女やで、あんたホンマに…」
渋谷で降りた。愛子の好きな映画俳優が自作絵画の個展をやっているという。その俳優とは仕事をしたことあると俺が言うと、愛子は心底羨ましがった。
雲ひとつない冬晴れだった。街を歩くアベックは楽しそう。俺たちもその景色に溶け込めている気がした。愛子は今か今かと個展会場にたどり着くのを待ちきれずに興奮していた。俺たちは、つい昨夜に心中しようとした男女には到底思えなかった。おかしいで……。ホンマに…。俺は笑った。
*
三度目のセックスを終えて、俺たちは愛子のアパートのシングルベッドで、ぐったりと仰向けになった。コンドームを取り外して、無造作にゴミ箱に放り投げた。入った。たぶん。電気は消えてるからよく見えないのだ。
午前二時。半分開け放したカーテンから月と都会のネオンだけが狭い部屋にさらさらと差し込んでいた。暖房をつけていないから、外気は十度にも満たないだろうに、俺も愛子も全身にじんわりと汗をかいていた。ちびまる子ちゃんみたいな髪型の愛子の後ろ髪が、首筋にべっとりと絡みついていた。俺はその後ろ髪を左手の中指と薬指の爪で、すっと、ひっかけた。遠くから、たぶん、隣のアパートの部屋からか、アコースティックギターの旋律が漏れ聞こえていた。それ以外は、ほとんど完璧な静寂が二人寝転ぶ空間を、やさしく包み込んでいた。
「あんなぁ」と、愛子が囁いたのが全ての始まりだった。
「どないした」
「毎日こんなに楽しくてええんかなって、最近思うねん。この気持ち、あんたわかる?」
俺は沈黙した。わかると思う。確かに俺たちはしたたかに幸せで、相性も最高だった。二人とも大阪出身で、ほとんど同じタイミングで東京に来て、この巨大な、何もかも飲み込みそうな街で、奇跡的に巡り合ったのだ。
趣味も、身体も、生活スタイルも、二人は共鳴できた。
俺は映画監督の見習いで、愛子は油絵の画家。本業ではお互い食っていけないから、渋々アルバイトもして生計を立てていた。
俺のアパートには風呂がないから、週の4、5日は愛子のアパートの世話になった。23区内の二駅離れた所に俺たちは生息している。俺はママチャリをかちゃかちゃと漕いで愛子のアパートに通っていた。
「どないしたん、暗い顔して」
「わかるよ」俺は言った。
「やんなあ」
「じゃあさ、心中せえへん?」愛子はボソリと呟いた。
「……」
「ウチ、いま死んでも後悔せえへんと思うねん。これ以上今より楽しいこともないと思うし。だったら今死んだらこのままでおれる気がする。ウチも、あんたも」
「本気で言ってるんか?」
「本気やで」愛子は俺の目をキッと見つめた。
「じゃあ、俺を先に殺してくれ。お前の死んだ顔はみたくない」
「わかった」
と言って、愛子は起き上がり、俺の体の上にまたがった。それから俺の首をぎゅーーーっと締め付けた。俺は目をつむった。酸欠になった。意識が遠のいてゆくのが自分でもわかる。俺は両手で愛子の小さな乳房をぎゅっと掴んだ。「ハアハアハア」と蚊の鳴くような声を漏らしているのが、俺なのか、愛子なのかわからなかった。思考も停止しそうだ。
「ウチの首も絞めて」と愛子が言った気がした。多分そう言ったはずだが、どうやら聴覚がかなりイカレてきたらしい。俺は夢中で愛子の首をきつく締め上げた。
「んんーーーーー」
「っかーーーー」
「ァァァァァァァァアァァァァアァァァ」
「らクァラーーーーーーーーーーーーーーーーアアア」
「@$#^@&#*&%@」
「*&&#*#&#*#%$*@@&$&」
ひどい悪夢をみた。幻想と言うべきか。天国と地獄を行ったりきてるしている感じ、黒い顔をして斧を持った死神が、俺を追いかけ回した。ああ、死ぬんやなあ、と俺はぼんやり思った。どうにでもなれ、もうどうにでもなれ、俺の人生こんなもんや。束の間の幸せ。それで充分。ああ! ああああああああああ!!! 勝手にしやがれえ!
*
朝になった。俺は生きていた。生きてしまっていた。
隣で眠る愛子をみた。俺の絞めた跡が首に、ほんのり赤く残っていた。
愛子の口に、顔を近づけた。愛子の吐く生ぬるい息が顔に当たった。俺はそっと、愛子の頰にキスした。
俺はベランダに出て、ハイライトに火をつけて吸った。ややあって、愛子も目を覚まし、こっちにきた。愛子は俺のハイライトを水色の箱から一本取って、百円ライターで火をつけて、美味そうに吸った。くそ眩しい太陽の光が二人を照らした。
*
絵画個展に主催者の姿はなく、絵も想像していたより凡庸だったことに愛子はプンプンした。
「サーティーワン行こう! なんだか無性にアイスクリームが食べたい!」
「はいはい、行きましょう」
そうやって俺たちは歩き出した。
俺たちはどこにサーティーワンがあるのか皆目知らなかった。当てもなく街を歩いた。スマホに頼る訳でもなく、ましてや人に道を聞いたりもしない。でも、いつかたどり着けるさ。
俺は渋谷を歩いている。隣には俺の彼女がいる。
俺も彼女も果てしない未来がある。他に何を求める?
人生はこれからまだまだ続くのだ、死にたくても、生きたくても。